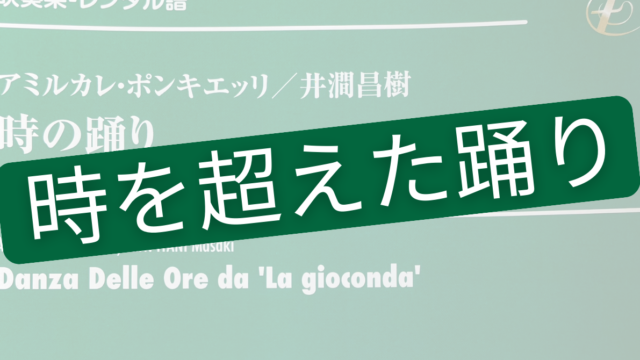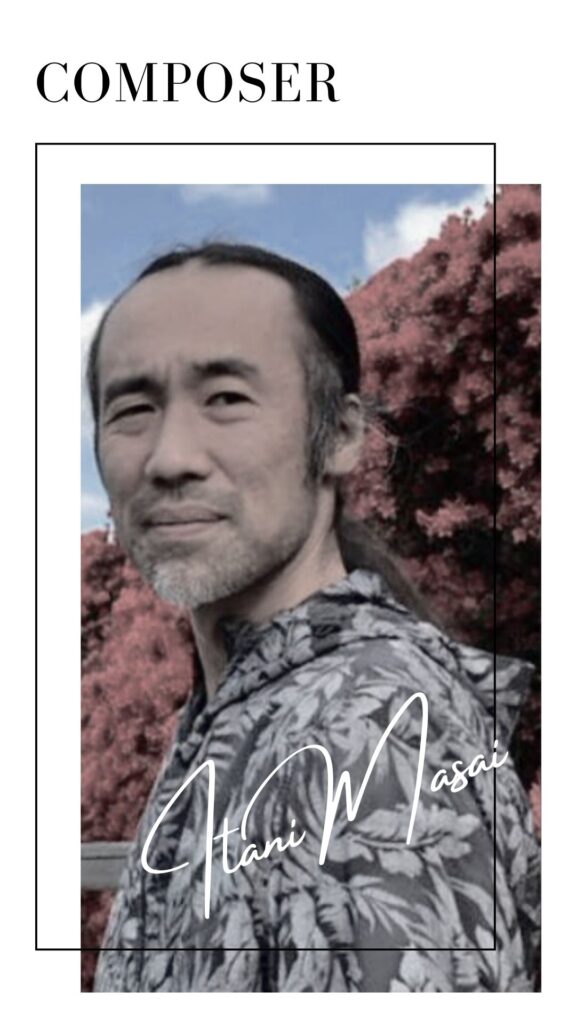何年前の出来事だったか。
電車のシートに腰掛けて、何を考えるでもなくボーッとしていると、同じ車両に居合わせた小さな女の子が大きな声で泣き出した。
「うさちゃんの手が千切れてる」
「痛い、って」
「早く病院に連れて行ってあげて!」
確かに、手に抱いていたうさぎのぬいぐるみの手がもげかかっていた。
隣にいた母親に必死に訴えかける声を聞きながら、私は本当に驚いた。
そうだった。
彼女のぬいぐるみは生きているのだ。
大切なぬいぐるみの腕の破損を嘆いているのではない。
大切な友達が負傷した腕の痛みに心が締め付けられているのだ。
本作品の曲目解説の一部を引用したい。
女の子にとって、飯事(ままごと)は慈愛に満ちたものだったはず。男の子にとって、戦隊ごっこは真に勇気と誇りを懸けるものだったはず。私たちが抱いていたぬいぐるみは生きていたはず。そこには、温度を持った感情があったはず。大人になったから虚構だと気付いたのではなく、それらを虚構だと切り捨てたから、私たちは大人になった。一種のノスタルジアだろうか。然し乍ら、人はどうして、その豊かな想像力を失うのだろうと寂しく思う。
現実社会において、共感には限りがある。
世界のどこかで飢えている子どもを思い浮かべながら、食事の時間は過ごせない。
想像力もまた、成長とともに姿が変わっていなければならない。
40を超えたおっさん(私です)が電車で「うさちゃんが・・!」などと泣いていたら、どうかそっと距離を取ってほしい。
仕方のないことなのだ。
ピーターパンはいない。
曲目解説は以下のように続く。
スコアの所々に記された「王女の庭」「おもちゃの兵隊」などの語句は、私の個人的な記憶。解釈の端緒になるならとの思いから、そのまま表記しているが、特にストーリーがある訳ではない。思い出はいつも断片的で、脈略など無いのだから。
作品は大きく6つのシーンに分けられていて、最後は「もう戻れない」と冠した Presto の音楽。
これは恋をしたことによって “大人” にならざるを得なかった王女の心理を描きたかった場面だ。
作曲から10年以上経って、ふと考える。
“王女の心理” とは何だったのだろう。
なかなかどうして破壊的な Presto である。
子どもが大人にならないとはつまり、そこに時間が流れていないということになる。
それは異界だ。
全ての生命に等しく時間は流れる。
ある日突如として大人になるわけではないが、いつまでも子どもでいられるわけでもない。
全ての生命は常に刻々と変容を迫られる。
曲中に登場する「レジスタンス」とは、恐怖に対する抵抗。
人間にとって、多くの変容は大なり小なり恐怖を伴わないか。
特に子どもから大人にかけての成長に限れば、何とも過酷な戦いだったなと思う。
老いるよりも破壊的だ。
その過程に生み落とされた思い出のかけらは秩序なく散乱するだろう。
脈略など残っていよう筈もない。
作曲した当時は「鈍感になることこそが大人になること」と思っていたが、今はそこまで悲観的でもない。
悪いことばかりではないだろう。
遠く昔に置いてきた景色は他者の目を通じて感じ取れば良い。
これから私は、産まれたばかりの娘たちがこれから見るであろう景色を少しだけ隣で覗かせてもらおうと思っている。
このような思いを持ち得ただけでも、私は大人になれて良かったなと感じている。